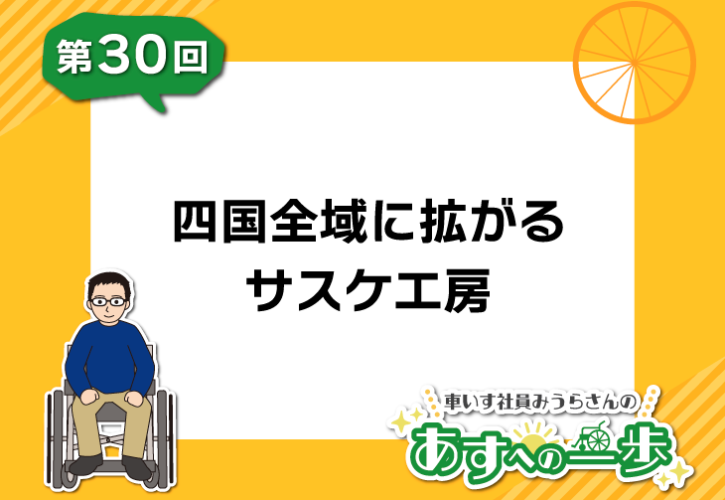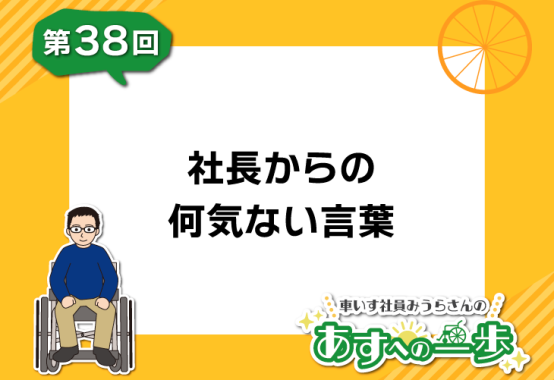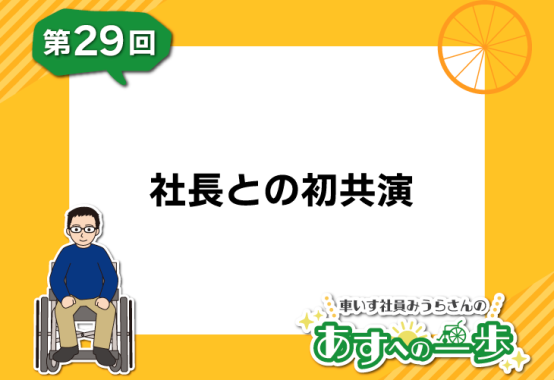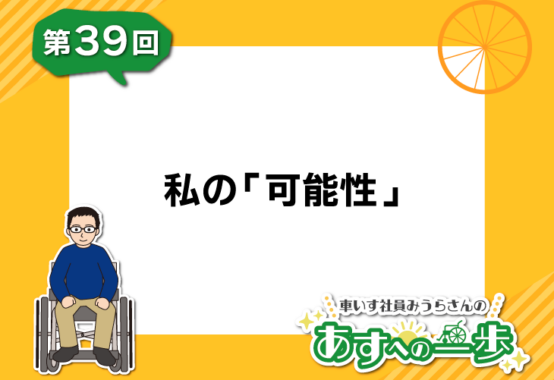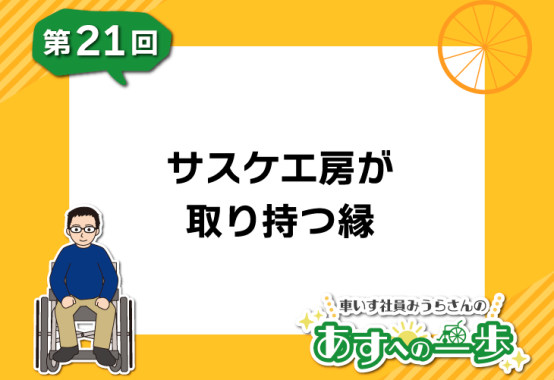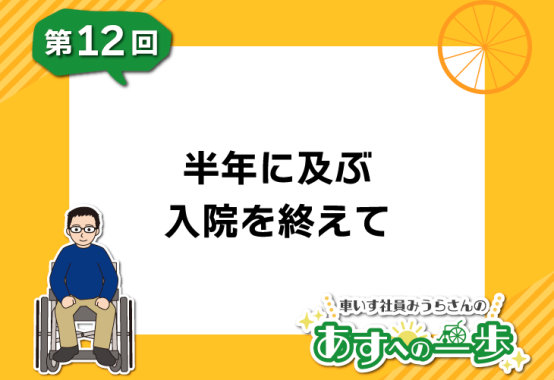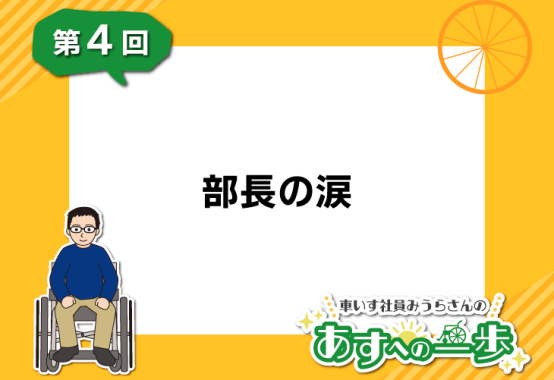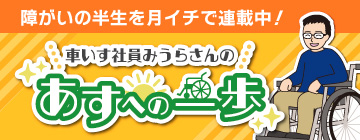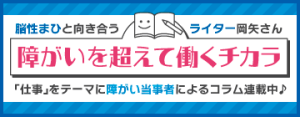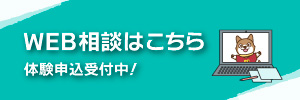2016年になり、サスケ工房に入ってから4年目を迎えた。
すでに事業所の数も6つと増え、四国4県すべてに進出を果たしていた。
そのなかで最古参の新居浜事業所では、利用者の人数もすでに30名を優に超えてきた。
朝礼も大人数となり、3年前の初期の頃のことを思うとたいへん感慨深いものがあった。
ただし図面という業務の性質上、全員が同じレベルで作業をすることについては依然として課題があった。
新規の利用者を含めて、なかなか実務に移ることができない事情の利用者に向けて、もっと体系的な指導体制を整備する必要があったのだ。
それについては、この春から正式に職員となるFさんが中心となって、限られた職員でも対応できるための新たにカリキュラム作りを進めていた。
また利用者が幅広く対応できるように、図面以外の業務も取り入れていくという話もあった。
例えば、デザインスキルがある利用者が中心となって、お付き合いのある関係機関からイラストレーターでのチラシ作成の受注を取り付けたりもしていた。
私も自分の知見を広げる意味で、一度そのチラシ作成業務に関わってみた。
ただ私の場合は、あくまでも図面チェックの作業がないときのための補完業務的な意味合いだったのだが、イラストレーターというソフトに初めて触れて非常に新鮮な気持ちだった。
しかし、デザイン業務に関してはやはりセンスが問われる面があり、何人かの利用者でそれぞれチラシ案を作成したのだが、最終コンペで私のものが選ばれることはなかった。
その一方で図面の実務に関しては、指導員のTさんとONさんが中心となって、図面チェックに関しても精鋭部隊によるチーム体制が確立されつつあった。
だんだんその業務量も増えてきたため、自ずと私はチラシ作成の業務からは遠ざかることになった。
Tさんに関しては、新しく加わった鳴門・高松・南国の指導も含めて事実上、全6事業所の上に立つ統括責任者的立場となっていた。
あるとき、他の事業所がどういったレベルなのかがちょっと気になったので、Tさんに聞いてみたことがある。
「西条、板野ではすでに職員並みの精度でバリバリ作業してもらっている利用者さんもいて、新居浜も追い抜く勢いですよ」
Tさんは冗談めかした様子で笑いながら私にそう発破をかけた。
それまでは特に他事業所のことを意識することもなかったのだが、Tさんからの何気ないその言葉に、サスケ工房の立ち上げ事業所としてのプライドのようなものが自然と沸いてきて、思わず心の中でつぶやいた。
「もっと頑張らねば」
花見でのギターイントロクイズ
3月に入り、今年も事業所行事として花見(実際には外でのものではなく、公民館の部屋を借りての懇親会的意味合いなのだが)をしようという話になった。
1年前のときの企画担当だった職員のSHさんが退職をしてしまったため、他の女性職員のNTさんから私に相談があった。
原則として、利用者が中心となって準備をし、それを職員がフォローするという主旨だったため、昨年末の忘年会での余興のこともあり、私に何かできないかということだった。
実は1年前の花見に参加したときに、SHさんと利用者のB君が中心となって、スマホを使ってのイントロククイズをしたのを見て、次はギターの演奏によるイントロクイズが出来たら面白いだろうなあということを思いついていた。
ということもあり、私は二つ返事で余興担当を引き受けた。
幹事役や会計は他の利用者に任せて、とりあえず私は3月末の花見に向けて約10曲分の歌謡曲のソロギターバージョン(ギター一本でメロディと伴奏を同時に弾く奏法)を毎週末練習した。
そして、桜がほぼ満開となった頃に花見の当日を迎えた。
お昼休みに入ると、歩いてすぐのところにある公民館に全員で移動した。
まずはみんなで花見弁当を食べながら、最近新しく入ってきた利用者の自己紹介からスタートした。
7人ほどの利用者が緊張しながらも約1分ずつ自己紹介をしたのだが、それぞれの趣味など普段知り得ないことなども知れたのはよかった。
続けて画伯と呼ばれるWさんが、かなりマニアックなクイズを披露し、みんなの笑いを誘った。
画伯は一見コワオモテなのだが、非常にユーモアがありそのギャップが魅力的だった。
そして、いよいよ私の出番となった。
忘年会の時同様、金髪のカツラを被り、まずはトーク中心でみんなを笑わせた。
そして、前回と同様にクイズに当たった人にはお菓子の景品をプレゼントする段取りで初の試みとしてギターイントロクイズを始めた。
新居浜事業所の利用者は20代から60代まで幅広いということもあり、できるだけみんなが知っている選曲にしたのだが、見事に全曲を誰かが当て、企画としては大成功だった。
景品をもらう利用者はみんな本当に嬉しそうだった。
「今日は楽しかった」
花見終了後の片づけの際に、方々からそんな声が聞こえてきて、「来年もまたやろう」と心に決めたのだった。
蜂窩織炎(ほうかしきえん)
4月に入ると息子も高校3年生となり、高校野球として最後の夏に向けて毎週末、四国中のいろんなところに遠征試合に行くようになった。
妻に関しては他の父兄との乗り合わせで毎回応援に行っていたのだが、私自身は体調のことを考えて応援に行きたいのを我慢し、家でひとり過ごしていた。
そのかわりに妻には試合の経過をコマメに送ってもらうようにしていて、息子が試合で投げるときはlineで必ず動画を送ってもらったりしていた。
三振を獲った動画には「よっしゃ」と一人で叫んだり、打たれた動画を見てはため息をついたりと、家にいながらも一喜一憂しながら応援をしていた。
たまに送られてくるのが遅いときは、どうなったのだろうとドキドキしながら待っている有様だった。
5月のGWは毎年恒例の2泊3日の九州遠征だったのだが、さすがに私に何かあったときのことを想定して、私をひとり家に残すわけにもいかず、夫婦ともに応援に行くのを断念した。
代わりに保護者代表のITさんから息子の動画を送ってもらったりしたのだが、相変わらず調子は上がらないままだった。
息子については投球フォームを変えたり試行錯誤を繰り返していたのが、なかなか結果に結びつかず、後輩たちの後塵を拝する状況が続いていた。
この遠征の結果で5月以降のベストメンバーは固まっていくという話だったので、思うような結果が出ず終わってしまったことについては自分のことのように落ち込んだ。
そして連休最後の日のことだった。
朝起きると何か体にだるさがあり、明らかな異変を感じた。
褥瘡については完治していて、前の日も妻に点検してもらったところで特に何もない状態だったので、一瞬訳が分からなかった。
体温を測ると37度の微熱があった。
念のため妻に再度お尻をみてもらったところ、やはり褥瘡が出来ているわけでもなかった。
たぶん息子のことで気を揉んだことによる知恵熱だろうと思い、とりあえず一日中横になって安静に過ごした。
しかし、翌朝起きるとその日から仕事だというのにまだそのだるさは取れず、体温を測るとすでに38度に達していた。
お尻を点検するとやはり褥瘡などはなかったのだが、前日よりやや熱を帯びていて、腫れているようにも見えるという。
これまでにない症状に戸惑いながらも、事業所にその旨を報告しそのまま病院に向かった。
そして先生に診断をしてもらった結果、その原因がようやく判明した。
「蜂窩織炎(ほうかしきえん)ですね」
先生からの初めて聞くその言葉にしばらく呆然とした。

サスケ業務推進事業部
36歳の冬、先天性の脊髄動静脈奇形を発症。 リスクの高い手術に挑むが最終的に完全な 歩行困難となり、障がい者手帳2級を取得。当時関東に赴任していた会社を辞め、地元の愛媛新居浜に戻り、自暴自棄の日々を過ごす。
41歳の冬、奇跡的にサスケ工房設立を知り福祉サービス利用者として8年半、鉄骨図面チェックの仕事に従事する。 50歳で一念発起しサスケグループ社員となる。
これからの目標・夢
障がいで困っている人の就職のお役に立ち、一人でも多くの仲間を増やすこと。