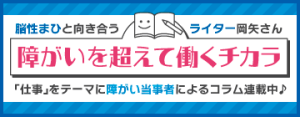それぞれの人生
入院当初から、私は4人部屋の病室で過ごしていた。
何人もの人が私より後に入ってきては先に出ていった。
中には私の病状よりも深刻だと思われる患者もいたが、その誰よりも長い入院となっていた。
褥瘡はガンなどのように直接的に命を脅かすものではないが、とにかく時間がかかるのだということを相対的に実感したものだった。
そしてもう一つ、この入院で実感したことがある。
それは当たり前ではあるが、人それぞれに人生のドラマがあるということだった。
苦しんでいるのは自分だけではない。
それぞれ事情、病気は違えど、それを乗り越えようと頑張っている人達と直に触れ合うことができたことは、落ちこんでいた私にとって大きな励みとなった。
私がMさんに仕事を辞めると告げたときは、隣のベッドには胃ガン摘出手術で入院していた66歳のNさんがいた。
Nさんは奥さんを早くから亡くし、男手一人で一人娘のお子さんを育て上げたという。
その娘さんはすでに結婚をして、旦那さんの仕事の関係で当時海外に住んでいた。
つまり、Nさんのそばには家族がいない状況で、唯一近くにいるお姉さんがその都度付き添いをしていた。
そんなたいへんな状況だったにもかかわらず、気落ちしていた私のことを察してか、毎日のように冗談を言って笑わせてくれたことが今でも懐かしく思い出される。
Nさんの優しさで随分と気持ちが和らいだものだった。
また私の向かい側のベッドでは、末期ガンの寡黙な77歳のKさんがいたのだが、足繁く病室に通う家族の姿から、あらためて支えてくれる家族の大切さも痛感した。
「お父ちゃん、頑張ってよ」
と泣きながら、旦那さんの手を甲斐甲斐しくさすり続ける奥さん、Kさん夫婦の姿が今でも目に焼き付いている。
その後、症状が重くなり個室に移られたため、どうなったのかまでは知る由もなかったが、奥さん以外にも息子さんや娘さん、そしてお孫さんからの電話での励ましの会話を幾度となく聞いた。
その様子から、Kさんがいかに家族を大事にしてきたのかがわかった。
自分の先の想像などしたこともなかったが、このときだけは自分に置き換えていろいろと考えずにはいられなかった。
そんな周りの影響もあり、私はこれくらいのことで落ちこんでいる場合ではないという気持ちに少しずつ変わっていった。
看護実習生
入院してから4ヶ月目となる10月になり、ようやく最終的な移植手術に辿り着くことができた。
手術は右側坐骨部周辺の皮膚組織を切り取って、褥瘡部分に移植をさせるという大がかりなものとなった。
全身麻酔だったため途中の記憶はなかったが、手術を終えるのに約4時間かかった。
術後、先生からは特にトラブルもなく順調に行えたという説明があった。
そして続けて、1ヶ月間はベッド上での座位禁止だということを告げられた。
移植した組織が内部でうまく癒着するまでは、創部に対して体圧などの負荷をかけてはならなかったのだ。
ここで一番たいへんだったのが食事のときである。
つまり、まっすぐ寝た姿勢のまま食事をとらなければならず、首を少しでも起こせるよう、二つ分の枕をかますようにした。
最初は味噌汁などの汁物をメニューからカットしていたが、徐々に要領を得てきて、座位禁止後1週間経った時点で通常のメニューに戻してもらうようにした。
創部の経過も順調だった。
そして予定の1か月を終え、まずは食事のときのみという条件から、徐々に座る時間を増やす段階に入った。
完全寝たきりの期間として1か月は多少苦痛ではあったが、特に熱を出すこともなく、ここにきて退院というゴールを意識し始め、精神的にもゆとりが出てきたように思う。
またこの頃から、病院に隣接している看護学校の1年生が2週間ほど看護実習をすることになり、一人の女の子が看護学校の先生と一緒に私のところへ訪れた。
「三浦さん、手術後の療養でたいへんなところですが、出来ましたらこちらのIさんの実習担当患者さんになっていただきたいのですが」
先生がそう紹介したIさんは、まだあどけない表情で実際の患者を前にして幾分緊張しているようだった。
おそらく本人にとっては、決して担当したい患者ではなかったかもしれないが、私自身はその子の様子から何か清涼感のような瑞々しさを感じて逆に救われたような気持になっていた。
その純粋な感覚がどこか懐かしく、二つ返事で承諾した。
それから毎日のように、Iさんは私のところへ来るようになった。
1年時の看護実習はどちらかというと技術的なものではなく、とにかく実際の患者とコミュニケーションを取ることが主だった。
私の障がいのことについて、Iさんなりに一生懸命聞いてきた。
私の経験が彼女に何かしら響けばいいという思いで、包み隠さず丁寧に説明した。
するとその話を聞いたIさんはうっすらと涙を浮かべていた。
何日か経つと最初は緊張していたIさんもすっかり打ち解けてきて、本来持っていたと思われる明るさが出てきた。
私もその波長の影響か、随分と楽しい気持ちで過ごすことが出来た。
私は一人息子をもつ親の立場ではあったが、こんなに純粋な娘を育てた親の顔が見たいと思わされるほどだった。
半年に及ぶ入院を終えて
Iさんの看護実習中に、いよいよ退院に向けたリハビリを開始し始めた。
季節はすっかり冬の12月となり、すでに入院してから5か月が過ぎていた。
車いすに乗り移ること自体が、入院して以来だったので最初はかなり不安があった。
最初は担当理学療法士のSさんに体を支えてもらいながら移乗したが、数日のうちに以前の感覚を取り戻すことができた。
「もうちょっとで退院ですね」
リハビリにも付き添っていたIさんが、病室に戻る途中に笑顔で私に話しかけてきた。
その笑顔は、かつての自分が営業時代に振りまいていたものとは違う、心の底からの笑顔に映った。
これは、決してIさんだけに感じたことではなかった。
関わった多くの看護師さんに共通する部分であり、本人は無自覚かもしれないが、そういう心根が伝わってくる人たちが、なるべくして看護師になるのだろうと思わされた。
そうこうしているうちに、あっという間に2週間が経ち、実習最終日をむかえた。
ちょうどその日は、毎年の恒例行事となっている入院患者対象のクリスマス会が、病院の1階ロビーで行われていた。
私はIさんに車いすを押してもらいながら初めてそのクリスマス会に参加した。
同じ病棟で受け持っていた男性看護師のUさんが、他の看護師によるギター伴奏で、「なごり雪」などの歌を披露していて、そのうまさに驚かされた。
参加していた患者のほとんどが高齢の方ばかりだったが、それらの年代に合わせた選曲ばかりで、どの患者の表情も活き活きしていたのが今でも印象に残っている。
クリスマス会が終わったあと、Iさんと一緒に病室に戻り、いよいよ最後のときがきた。
「今日で、車いすを押してもらうのも最後やね。Iさんのおかげで、この2週間ですっかり元気になったよ」
私がそういうと、Iさんはほんとうに嬉しそうな笑顔を見せた。
「Iさんは素直で明るくて優しいから、きっといい看護師になれるよ。勉強頑張ってね」
私が続けてそう言うと、Iさんはみるみるうちにポロポロと涙を流し出した。
私にとっては正直な気持ちを伝えたまでだったのだが、Iさんにとっては予期せぬ言葉だったのかもしれなかった。
「いろいろと優しく接していただいて、本当にありがとうございました」
Iさんは泣きじゃくりながら、最後の別れに対する感謝を伝えてくれた。
このように入院中には、普段では得難い出会い、経験をたくさんさせてもらった。
そしてその後は特に問題もなく、人生で初めてとなる病院での年越しを経て、2012年1月に晴れて退院することができたのだった。
実に半年間に及ぶ長い長い入院生活だった。

36歳の冬、先天性の脊髄動静脈奇形を発症。 リスクの高い手術に挑むが最終的に完全な 歩行困難となり、障がい者手帳2級を取得。当時関東に赴任していた会社を辞め、地元の愛媛新居浜に戻り、自暴自棄の日々を過ごす。
41歳の冬、奇跡的にサスケ工房設立を知り福祉サービス利用者として8年半、鉄骨図面チェックの仕事に従事する。 50歳で一念発起しサスケグループ社員となる。
これからの目標・夢
障がいで困っている人の就職のお役に立ち、一人でも多くの仲間を増やすこと。