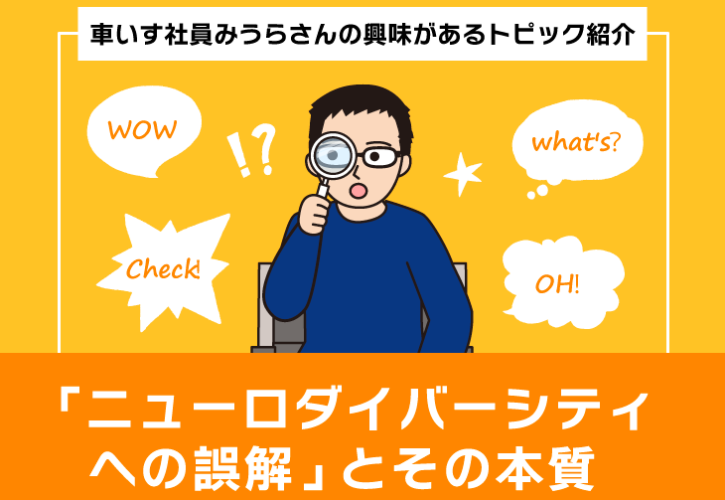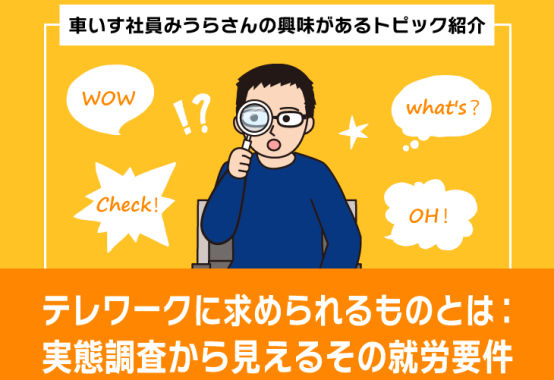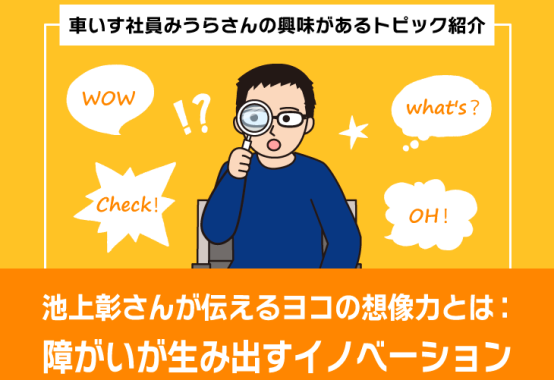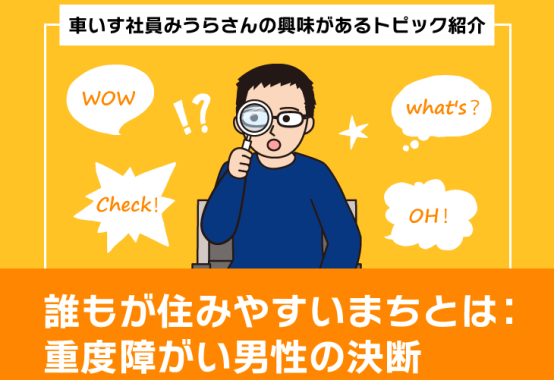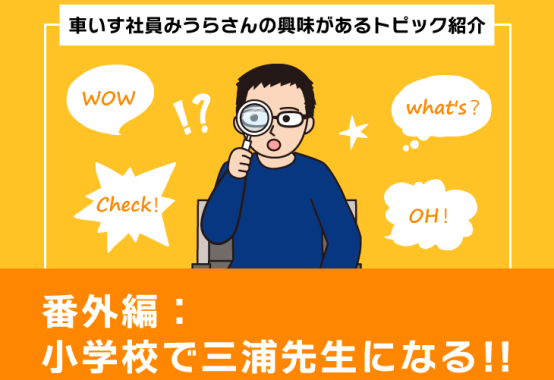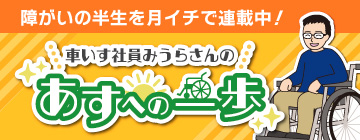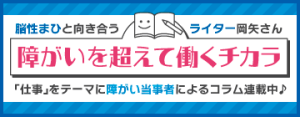「ニューロダイバーシティ」という言葉が近年注目を集めていますが、その実態や目的についてはまだまだ誤解が多いように感じます。
今回取り上げた記事『“脳の多様性”を社会で活かす「ニューロダイバーシティ」の現在地』では、北本英光氏、関島勝巳氏、伊藤穣一氏の対談を通じて、ニューロダイバーシティの本質に迫る重要な視点が提示されていました。
以下では、対談での発言を引用しながら、その誤解と本質について考察したいと思います。
“ニューロダイバーシティはそのような限られた人々のみの話でも、さらには発達障がいと診断がついた人のみの話でもない。すべての人の『多様な特性の脳』に向き合う姿勢が大事です。”(北本氏)
この発言からわかるように、ニューロダイバーシティは発達障がい者だけに限定される話ではなく、社会全体の多様性を尊重する考え方であるべきです。
しかし、現実には「発達障がい=天才」「特異な才能を持つ人の話」といった誤解が根強く存在しています。
関島氏もこの点を指摘し、「発達障がいの人が天才だとか天才ではないとか言いたいわけではない」とし、「ほとんどの発達障がい者は普通の能力の人」であることを強調しています。
“私は発達障がいの人が天才だとか天才ではないとか言いたいわけではありません。『発達障がい=天才』という図式に、発達障がいの人自身が違和感を覚え苦しんでいることも見聞きし、ニューロダイバーシティについて関心を持つようになりました。”(関島氏)
この言葉は非常に重要です。
世間のイメージが狭く特定のステレオタイプに固まってしまうことで、当事者が自身の実情と乖離した評価に苦しむことがあるからです。
ニューロダイバーシティの本質は、誰もがそれぞれの特性を持つ「普通の人」として認められ、多様な働き方や生き方を尊重することにあります。
また、伊藤氏は日本の社会文化に根付く「秩序」や「標準化」の美学が、多様性の受容を難しくしていることを指摘しています。
“ニューロダイバーシティで重要なのは標準化ではなく、各自がそれぞれの方法で取り組むこと。それは、日本のそうした美学や教育の仕方とはなかなか合わないんです。”(伊藤氏)
これには深く共感します。
日本の教育や職場の風土は長らく「普通」や「標準」に合わせることを良しとしてきました。
そうした環境下で、特性の異なる人を「変わっている」「異質」として排除や矯正の対象としがちです。
しかし、教育における苦手を克服する取り組みだけでなく、得意を伸ばすことが大切であるという伊藤氏の指摘は極めて示唆的です。
“教育には苦手分野や弱点を引き上げる方法と、強みの方を伸ばす考え方があります。日本の仕組みでは前者が主で、本人の得意分野に力を入れるのではなく苦手を一生懸命無くそうとする。けれども、特徴的な人材が育つのはやはり後者の方法です。”(伊藤氏)
また関島氏も企業現場における現実として、障がい者雇用は法定雇用率という「義務」が背景にあり、「義務」と「希望」は必ずしも一致しないことを以下のように述べています。
“「内発的動機」「外発的動機」という観点で考えると、現状では多くの障がい者は法定雇用率、つまり「法律的な義務」をベースとした環境の中で仕事をしていることが多くあります。義務からは自由な発想は生まれにくいと思いますので、現在の状況では本来の「内発的動機」に基づく働き方が十分に実現されているとは限りません。”(関島氏)
この現実は、当事者の「内発的動機」を削ぐ要因の一つであると感じます。
伊藤氏も、「褒められるために頑張る」ことが子どものモチベーションになり、それが大人になっても続くことで内発的動機を失い、「褒められ中毒」になってしまう危険性を指摘しています。
“たとえばASDの子は目線をなかなか合わせられないので、合わせると褒めてご褒美のクッキーを渡すような方法を取ります。本来は目線を合わせるのはコミュニケーションのためですが、ASDの子は違和感があるからしない。そこでご褒美をもらえるからするというモチベーションを植え付けてしまうと、部屋に入るなり手を差し出すようになってしまいます。”(伊藤氏)
この問題は単に発達障がいの子どもだけの話ではなく、一般の社会人にも通じるものがあります。
企業でも評価や認知のための外発的動機に偏りがちで、本来の「やりたいからやる」という内発的動機を尊重することがまだまだ不足していると言えます。
さらに、伊藤氏は支援のあり方にも言及し、障がい者支援の本質は「支援する」「される」の一方向の関係ではなく、当事者自身を現場に巻き込み、ともに作り上げていくことが重要であると説いています。
関島氏も、企業の障がい者雇用における「普通」のあいまいさに触れ、そこを超えるために個々の特性を尊重した柔軟な働き方が必要だと述べています。
“多くの企業の障がい者雇用の現場では、支援する側が「支援される側に対して”普通の仕事の進め方”をサポートすること」が一般的です。しかしこの「普通」の定義が曖昧であり、その不確かさの中で双方が気を遣いながらコミュニケーションを図っているのが現状だと思います。この課題の解決策の一つとしても、ニューロダイバーシティの考え方は有用だと思います。”(関島氏)
また、伊藤氏は当事者が能力を発揮するためには、親だけでなく、第三者の理解者や愛情ある支援者の存在が欠かせないと語っています。
これは、才能の開花には多様な人の支えが必要だという現実的な視点であり、社会全体での支援体制の重要性を示しています。
こうした支援の具体例として、NSITのセラピストが子どもに寄り添い、親が気づかなかった子どもの「喜び」の声を理解し、信頼関係を築いていく様子が紹介されています。
これは、障がいのある子どもとその家族にとって新たな気づきをもたらす大切な支援の形だと感じます。
最後に、ニューロダイバーシティに関して最も根深い誤解は「多様性の価値をどのように社会が受け止めるか」にあると思います。
伊藤氏が指摘したように、日本の文化的背景には標準化や秩序への美学が強く、多様性を容認しきれない面があります。
だからこそ、社会全体の意識を変え、当事者を巻き込みながら多様性の価値を再定義していく必要があります。
“日本では特に産業革命以降、ダイバーシティ(多様性)を美学として捉えない傾向がある。どちらかといえばピシッとそろった秩序あるものや、標準化された人々が足並みをそろえて仕事をする方が美しいという美学と、その背景としてフェアネスを尊ぶ文化があるのではないでしょうか。”(伊藤氏)
このような背景があるからこそ、ニューロダイバーシティに対する誤解や偏見が生まれ、広がってしまうのだと改めて理解しました。
以上のように、本対話からは「ニューロダイバーシティに対する誤解」がなぜ起こるのか、その背景にある文化的・社会的な要因や、誤解による当事者の苦しみ、そして解消に向けた具体的な取り組みの重要性が見えてきました。
これらを踏まえ、私たち一人ひとりがニューロダイバーシティの本質を理解し、多様性を尊重する社会の実現に向けて行動していく必要があると強く感じました。

サスケ業務推進事業部
36歳の冬、先天性の脊髄動静脈奇形を発症。 リスクの高い手術に挑むが最終的に完全な 歩行困難となり、障がい者手帳2級を取得。当時関東に赴任していた会社を辞め、地元の愛媛新居浜に戻り、自暴自棄の日々を過ごす。
41歳の冬、奇跡的にサスケ工房設立を知り福祉サービス利用者として8年半、鉄骨図面チェックの仕事に従事する。 50歳で一念発起しサスケグループ社員となる。
これからの目標・夢
障がいで困っている人の就職のお役に立ち、一人でも多くの仲間を増やすこと。