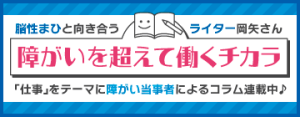脊髄動静脈奇形
「せ、せきずいどうじょうみゃくきけい?」
聞きなれない言葉に、医師から受け取った言葉をそのまま私はなぞるようにオウム返しした。
医師はレントゲン画像に映し出された私の脊髄の中の血管を指差した。
その先には、本来分かれているはずの動脈と静脈が絡まり合うかのように膨らんだ影があった。
数か月前から左足に力が入らなくなっていた原因が、やっと5つ目の病院で突き止められたという安堵の気持ちと、聞きなれない病名に対する不安とが同居しながら、医師の次の言葉を待った。
「脳ではよくあるのですが、脊髄ではごくまれな病気で、100万人に1人レベルの先天性の病気です。三浦さんの場合は下肢に影響を及ぼしていて、このままだといずれ完全に歩けなくなります。」
最後の言葉はにわかには信じられなかった。
そんな病気があることなど知る由もなかったが、歩けなくなることなど想像もできなかった。
背筋が凍る思いがした。
「治すことは可能でしょうか?」
恐る恐る聞くと医師は少し複雑な表情を浮かべた。
「残念ながらこの国立病院では難しいです。関東全体で見ても指を折るくらいしか症例のある先生はいないのですが、幸いこの群馬にお一人だけいらっしゃいます。その先生に紹介状を書きますので、一度受診されてください。」
その言葉で少し救われた気がした。
その先生にお願いするしかない、歩けなくなるなんて絶対いやだ。
自分には、これまで急遽の転勤にも黙ってついてきてくれた妻や小学3年生の息子がいる。
もともとゆかりのないこの地で、家族にこれ以上負担をかけさせるわけにはいかないのだ。
リスクある手術に挑戦
紹介された先生は想像していたよりも穏やかで、庶民的な先生だった。
とても国内で限られた症例実績のある先生とは思えなかった。
しかし、説明を聞くうちにその優しそうな目の奥にある絶対的な自信のようなものを感じた。
そして、リスクの話も聞かされた。
カテーテルを大腿部付け根から入れ、膨らんだ血管患部のところまで伸ばし、アロンアルフアのような液体を膨らみのスペース分だけ注入するという、まさに針の穴を通すような手術だった。
先生の指さばき次第で、もし失敗すれば上半身にまで影響が及ぶというリスクがあった。
そのリスクが書かれた同意書に私は迷わずサインをした。
もう、治したい一心だった。
この先生ならきっと治してくれるはずだ、いや絶対に治して新拠点予定の新潟での営業所長になるんだ、そんな希望と野望がすべての不安、心配を吹き飛ばしていた。
2007年12月13日、愛媛から両親もかけつけ、私は最愛の家族に見守られるなかその手術に挑んだ。
全身麻酔を打たれるなか、心配そうに見送る母親の顔を浮かべながら、徐々にその意識が薄れていくのだった。
手術は実に5時間にも及んだ。
人生で一番泣いた日
目が覚めると、周りには先生と両親、妻、息子が周りを取り囲んでいた。
まさによくドラマで見るようなシーンだと思った。
まだ頭がぼうっとしているなか、おもむろに先生が声をかけてきた。
「手術自体は予定の2/3までは塞ぐことができました。まずゆっくりでいいので手を動かしてみて」
一瞬、リスクの話を遠い昔のことのように思い出し緊張が走ったが、問題なく手は動いた。
「では左足のほうを動かしてみて」
先生がそう言うと、さらに緊張感が増した。
予定の2/3まで閉じたのだからきっと大丈夫だと心で言い聞かせながら動かそうとした。
しばらく先生は沈黙を保っていたが、やや遅れてもう一度同じセリフを口にした。
すでに動かしているつもりだったが、先生の目にはそう映っていなかったのだ。
手術前は少し引きずって力が入らない程度だった左足が、術後の今は必死で動かそうとしても微動だにしない。
いやな予感がした。
まだ訊かれてもいない右足をもしやと思って動かそうとした。
同じだった。
右足は何の問題もなく動くはずだった。
しばらくその現実を受け入れることが出来ず、先生の指示に関係なく両足をなんとか動かそうと必死でもがいた。
もがけばもがくほどに、その厳しい現実を突きつけられるだけだった。
自分でも予期せぬタイミングで涙が溢れた。
ついで押し寄せるように嗚咽をもらした。
皆に見られるなか、その顔を両手で覆った。
覆えば覆うほど嗚咽はひどくなり、体が揺れた。
こらえることはできなかった。
どのくらい泣いたかは覚えていない。
しかし、間違いなく人生で一番泣いた日だった。

41歳の冬、奇跡的にサスケ工房設立を知り福祉サービス利用者として8年半、鉄骨図面チェックの仕事に従事する。 50歳で一念発起しサスケグループ社員となる。
障がいで困っている人の就職のお役に立ち、一人でも多くの仲間を増やすこと