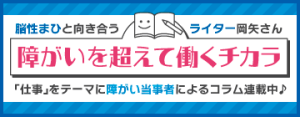変わらざる得ない事情
前回の入院のときもそうだったのだが、入院して何が苦痛なのかと言えば、毎朝看護師さんに陰部の清拭をしてもらうことだった。
それも毎日担当が変わるため、結果的に10人以上いた担当チームのすべての看護師さんにそれをしてもらうことになり、表面的には照れ隠しで雑談などしながら平静を装ってはいたが、内心は嫌なものでどこまでいっても慣れるものではなかった。
ある種の拷問のようなもので、半分冗談ではあるがこんな目に合うのなら二度と入院なんかしたくないと思ったりもした。
それでも看護師さんからは毎日元気をもらっていたのは確かで、私も話し出すと割とずっと話してしまう気質があったため、ある時あまりの長話に相部屋の入院患者が、話相手をしてくれていた看護師さんにどなりつけるというような苦いこともあった。
相部屋の患者さんについてはやはり入れ替わりが目まぐるしかったが、そのなかでも脳梗塞で倒れ急性期病棟から移ってこられた佐藤さんという55歳の男性のことが今でも忘れられない。
奥さんに車いすで押してもらいながら部屋に初めて入ってきたとき、たまたまカーテンをオープンにしていたので目が合うや否や「こんにちは」と声をかけた。
しかし、奥さんから「佐藤です、これからお世話になります」と挨拶があっただけで、佐藤さん自身は私の目を見ても全くの無表情のまま挨拶を返すこともなかった。
私はまたやっかいな人が入ってきたなと思い、無視をされたことに半ば腹も立っていた。
隣でしばらく奥さんが佐藤さんに色々と話しかけていたが、カーテン越しに本人の声が聞かれることもなかった。
看護師さんが来てもそれは一緒で、脳梗塞によるショックで完全に心を閉ざしているのだろうと思い込んでいた。
それ以降、奥さんは毎日お昼以降にそれこそ甲斐甲斐しく病室に訪れていた。
そしてその週末となる土曜の午後にも奥さんはもちろん来ていたのだが、驚いたのはその日のうちにその佐藤さんに対して4~5組のお見舞いがあったことだった。
その会話を隣で聞いているうちに、佐藤さんが脳梗塞後に全く喋ることができなくなったこと、そして元々はおしゃべり好きで会社のなかでも部下への面倒見もよく、非常に人望の厚い人だったということがわかった。
「すっかり、顔つきも性格も変わってしまって・・・」
お見舞いにきた会社の同僚と思われる若い男女に向かって、奥さんは途中で声を詰まらせたのだ。
そのやりとりをカーテン越しに聞いたとき、私は自分を恥じた。
佐藤さんのほんとうのことも知らないくせに、表面的な様子だけで勝手に人のことを決めつけてしまったことについて反省した。
お見舞いの人たちの話を聞けば聞くほど、私なんか足元にも及ばないくらい佐藤さんは人格者であることがわかってきた。
病気によって余儀なく変わらざる得ないという現実を目の当たりにし、今の自分の苦しさは実は大したことではないのかもしれないと気づかされた。
予定通りの退院
二度目の手術をして以降は何もトラブルは起きなかった。
半月ほど入院期間が延びると思っていたのだが経過が思ったよりも良く、8月に入ってから完全座位禁止が解かれ、そのまま順調にいけば入院当初の予定通り2か月ほどで退院できる目途が立ってきたのだ。
そしてお盆過ぎにはリハビリを開始することになった。
担当の理学療法士のS先生とは、一人息子がいてしかも野球をやらせているという共通点があった。
S先生の息子さんは私の息子より一学年下だったが、学校の部活としてではなく市内の硬式野球チームでピッチャーをやっているとのことだった。
当然私以上に野球に対しての情熱や造詣も深く、この時期は夏の甲子園大会の真っ最中ということもあり、毎日のように二人で野球談議に花を咲かせたものだった。
そんなS先生の丁寧なリハビリ指導の甲斐もあり、8月の最終週には退院できるという話になった。
退院できること自体は嬉しかったのだが、問題は退院後のことだった。
サスケ工房でまた働くということについては、すでにHさんや白石社長からのお見舞いの時点で決めていたが、退院後にすぐ復帰するということについては全く自信がなかったからだ。
そこで、先生に退院後についてのことを相談した。
「出来れば1か月間くらいは自宅療養をして様子を見てから、そのあと仕事復帰されるのが良いと思います」
その先生から言葉を、そのままHさんにメールで報告をした。
するとすぐにHさんから返信があり、退院の目途が立ったことに対しての喜びの文言とともに、9月一杯は自宅療養をして問題なければ10月から仕事復帰するということでいいですよ、とのメッセージを確認することができた。
自宅療養についてはやや罪悪感のようなものを感じていたが、Hさんからの返信によって少し安心することができた。
妻が夕方病室に来た際にもそのことを話した。
「せっかくここまで来たんだから、変に焦ってもしょうがいないよ」
妻からそう言われ確かにそうだなと思い、この機会にしっかり治してから復帰しようと決意をあらたにした。
そして予定通り、8月最終週の日曜に私は無事に退院をすることができたのだった。
前例のない通所スタイル
この入院中に、実は2つ決めたことがあった。
ひとつはそれまでマンションの暮らしをしていたが、息子が高校生に上がるタイミングで、実家の横に家を建てて引っ越しをすることだった。
その理由としては、現状ではトイレが非常に狭く毎回便座に移動するのに結構な勢いをつけて移乗しており、それがお尻の褥瘡手術箇所に対してよくない環境だということと、実家の両親が近くにいることで妻の負担が何か軽くなればいいという思いからだった。
父親に協力をしてもらって、すでに松山の業者のほうで翌年の3月の時点までに転居が出来る計画を進めていた。
もうひとつは、入院中ベッド上で使用していた床ずれ防止用のエアマットレスを家でも導入することだった。
あらかじめ品番を控えておき、退院日までに地元の福祉用具業者に電動式折りたたみベッドとともにセッティングをしてもらっていたのだ。
2か月ぶりに家に帰ってくると、真っ先にその新しいベッドに寝てみた。
病院と同じものを購入したため、当然ながら入院中の環境と何ら変わらない感覚だった。
在宅での作業もここに移動式の長テーブルをかまして、ベッド上で作業すればいいということも思いつき、早速ホームセンターで注文をした。
現状出来ることと言えば、このような形で少しでもお尻の負担が軽くなるように環境を変えることだった。
しかし、それでも1か月後の仕事復帰のことを考えるとたまに不安が襲ってきていた。
午前中だけとは言え、毎日通所するということについてやや懐疑的になっていたのだ。
新しい環境を整えたことで、その不安はそのうちなくなるものだと思っていたのだが、日を追うごとにむしろ増大していく一方だった。
このままではいけないと思い、10月の復帰まであと半月となったときに、通院の帰りにサスケ工房に寄ってHさんに相談することにした。
「三浦さん、お久しぶりです。すごく元気そうで安心しました。少し太りましたか?」
Hさんが笑いながらそう話しかけてきたので、おかげで久しぶりの顔出しによる緊張が一気にほぐれた。
そして、入院中や自宅療養での様子をひととおり説明した後、いよいよ自分が今悩んでいることについて意を決して、Hさんに包み隠さず話した。
Hさんは私の悩みをうんうんとうなずきながら聞いた後、しばらく考えていた。
そして、何かの資料を取り出し確認後に、私のほうを向いてこう言った。
「では、10月から週1回だけ午前中2時間までの通所にしましょうか」
一瞬、そんなことが可能なのかと驚いた。
当然ながらそれまで前例のないことだったので、まさかそのような配慮をしてもらえるとは思っていなかったのだ。
今思えば、これがサスケ工房として初の週1通所の在宅スタイルの始まりとなったのだった。

36歳の冬、先天性の脊髄動静脈奇形を発症。 リスクの高い手術に挑むが最終的に完全な 歩行困難となり、障がい者手帳2級を取得。当時関東に赴任していた会社を辞め、地元の愛媛新居浜に戻り、自暴自棄の日々を過ごす。
41歳の冬、奇跡的にサスケ工房設立を知り福祉サービス利用者として8年半、鉄骨図面チェックの仕事に従事する。 50歳で一念発起しサスケグループ社員となる。
これからの目標・夢
障がいで困っている人の就職のお役に立ち、一人でも多くの仲間を増やすこと。