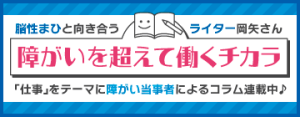退院後の引きこもり生活
2012年1月、半年ぶりに我が家のあるマンションに戻ってきた。
「父さん、おかえり」
息子からのその声を聞いて、やっと帰ってきたんだと実感した。
家の様子は特に変わりはなかったが、長い入院生活の反動か、妻と息子の家族三人でご飯を食べられるということが妙に新鮮で、それだけで幸せだった。
薄味の病院食にすっかり慣れていたため、妻の作る料理の味付けがより際立って感じられた。
食卓でのもっぱらの話題は、息子が入部していた軟式野球部のことだった。
「だいぶ腹筋がついたよ、ほらみて」
そう言いながら息子は服をめくり、その割れた腹筋を私に見せた。
しばらく見ないうちに随分と体が鍛えられるものなんだと感心した。
まだ中1で試合に出られる立場でもなかったが、毎日野球に関われるということが嬉しくてたまらない様子だった。
私も、そんな息子の話を聞くのが楽しかった。
顧問の先生、先輩、同級生のライバルの話など、息子なりに組織の一員として頑張っている様子が伝わってきて、そのことが頼もしく感じられたからだ。
しばらく接していないかった間に、息子は心身ともに大きく成長していた。
それに比べて私はどうだろうか。
新居浜に引き上げてきてからのこの3年ほどは、結果的に何も進歩がないと言えた。
せっかく手に入れかけていた仕事も、入院中に自らの意思であきらめてしまった。
あれだけ、働くことに前向きになっていたのに、今回の入院がその気持ちを全て萎えさせてしまったのだ。
トラウマとまでは言わないが、また同じようなことが起こったらと考えただけで、次に働こうという勇気は沸いてこなかった。
先を考えようとすればするほど気分は滅入り、仕事を手放してしまったことの後悔など、負の感情が出てくるだけなので、あえてそういったことを考えないようにしていた。
ほんとうは、外に出て色んな所に行ったりして気分転換をはかりたいところだったが、再発のリスクのことを考えるとそういうわけにもいかなかった。
結局のところ、退院後は食事とお風呂、そしてトイレ以外はほぼ一日中ベッドで過ごす日々の繰り返しだった。
毎日ベッド上ですることと言えば、テレビ視聴、iPad、新聞、本を読むことぐらいだった。
事実上、私はほぼ引きこもりの状態に陥っていたのだった。
安住の地に逃げる感覚
当時は、入院中も含めてベッドでたくさん本を読んだ。
サラリーマン時代はほとんど読書らしいこともしてこなかったのだが、大人になってあらためて知らないことを知るということは、私にとってよい気晴らしになっていた。
ジャンルは多岐に亘り、政治・経済・哲学・宗教・ビジネス書・純文学などありとあらゆる本を読み漁った。
働いていると、どうしてもそういったインプットの時間は限られてくる。
しかし、幸か不幸か、引きこもっていた私にはありあまる時間があった。
ベッドの上で誰にも邪魔されることなく、ただひたすらに読書にふけることができたのだ。
そんなこともあって、図書館と本屋にだけは、2週間に1回の頻度で通っていた。
図書館では、毎回上限冊数の10冊分借りるのが常だったため、返却までの2週間のなかで自分なりの読書計画を立てることが習慣となっていた。
この行為が、私にとっての唯一の生活のモチベーションとなっていた。
しかし、この読書というものが、私の将来に何かしら役に立つのだろうか。
当時は、本を読み切ること自体が目標であり、その先に何かを見据えたわけでもなかった。
つまり、ただ読みたいだけだった。
一種の活字中毒に近い状態とも言え、単なる自己満足行為だったのかもしれない。
あるいは、読書という完全に身を任せられる行為の居心地の良さに甘え続けていただけかもしれない。
それはある意味、私にとって一番楽なことだった。
そんな生活が、退院後は毎日続いた。
一度、妻が何気なく冗談で
「そんなに本ばっかり読んでどうするん」
と笑いながら聞いてきたことがあった。
単なる冗談の言葉ではあったが、私にとってはハッとさせられる言葉でもあった。
それは見方を変えれば、将来のことについて考えるのを完全にエスケイプした状態とも言えた。
先のことを考えると気持ちが持たないからこそ、読書という安住の地に逃げ込んだのかもしれなかった。
ある日、洗面所で鏡に映る自分の顔をいつになくじっくり眺めた。
自分でも驚くくらい、目には力がなく、全く覇気のない表情だった。
自己嫌悪の日々
そのような様子のまま、2012年も後半に差し掛かろうとしていた。
息子は一学年上の先輩が夏に引退したあとの、新チームのキャプテンとなっていた。
決してリーダーシップのあるタイプでもなく、また技術的にもキャプテンを任せられるようなプレイヤーでもなかったが、なんと自ら志願してキャプテンになったのだ。
どちらかというと人前では目立つタイプではなかっただけに、その息子の変わりように驚かされたものだった。
またキャプテンの親が、保護者会の代表も引き受けなければならないルールだったため、私の代わりに、妻がその役目を引き受けることになった。
他の部活と違って、野球部の場合は、親の立場としても比較的関わりが深い。
結果的に、親同士のつながりも強くなり、その分妻も週末は何かと忙しくなった。
私も、その流れでたまに週末の練習試合の応援に顔を出すようになった。
応援となると、多少の時間座り放しになるため、必ず帰ってからお尻に何かできていないかを妻にチェックしてもらった。
幸い、特に何かできることもなく、逆にそれまで引きこもっていた分、よい気分転換になった。
しかし、いいことだけでもなかった。
父兄同士の会話のなかで、普段仕事は何をされているかを聞かれることもあった。
これが案外、私にとってきついことだった。
当然ながら、どこの家庭でも父親は大黒柱として、何らかの職業に就いているわけだが、私はそのように答えることができない立場だった。
非常に肩身の狭い思いをしたのだ。
普段家にいるときは、できるだけ将来のことなど考えずに生活していたが、一歩外へ出れば、必然的にそこを避けて通れない場面があることをあらためて痛感させられた。
いつまでも今のままでいいわけがない。
あらためて、そう思い始めた。
しかし、そう思えば思うほど、かえって自分自身を追い込むことになった。
読書をしていてもあまり集中できなくなり、読んだはずのページをまた読み直すといったことも増えた。
日に日に気持ちだけが焦ってきていた。
しかし、いくら気持ちが焦っても、「会社に勤めるとすぐ体を壊してしまう」という固定観念が、それ以上先のことを考えることを妨害していた。
結局、就職先を探すというような具体的な行動もとらないまま時は過ぎ、季節は秋から冬に差し掛かろうとしていた。
その間、何ら行動に移せていない自分自身がだんだん嫌になってきた。
気持ちにも余裕がなくなってきたせいか、いつもなら聞き流せる妻の小言に対しても、いちいち声を荒げるようにもなった。
そんな自分がまた嫌になり、完全な自己嫌悪に陥っていた。
しかし、ここから状況は一変することになる。
11月のある日の朝、愛媛新聞を読んでいると、ある記事が目に飛び込んできた。
「新居浜の会社がNPO法人設立 障害者に設計業務指導」
これが、私にとって運命の出会いとなったのだ。

36歳の冬、先天性の脊髄動静脈奇形を発症。 リスクの高い手術に挑むが最終的に完全な 歩行困難となり、障がい者手帳2級を取得。当時関東に赴任していた会社を辞め、地元の愛媛新居浜に戻り、自暴自棄の日々を過ごす。
41歳の冬、奇跡的にサスケ工房設立を知り福祉サービス利用者として8年半、鉄骨図面チェックの仕事に従事する。 50歳で一念発起しサスケグループ社員となる。
これからの目標・夢
障がいで困っている人の就職のお役に立ち、一人でも多くの仲間を増やすこと。