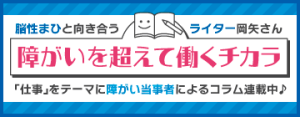妻の残りの人生
入院してから約2週間後、例によって左側太ももの皮膚から座骨部周辺にできた褥瘡への移植手術が行われた。
術後、先生からはもう左側太ももで移植できる皮膚はないと言われた。
3年連続同じ個所をやってしまったのだから無理もない。
写真で自分のお尻を見ると、継ぎはぎだらけの状態で、とても人のお尻のものとは思えない痛々しさがあった。
私は先生に恐る恐る訊いた。
「もし次に左側に褥瘡ができたらどうなりますか?」
そう言うと先生の表情がかすかに曇ったように見えた。
「お尻に大きな穴が開いた状態のまま、毎日その褥瘡と付き合っていく覚悟が必要です」
その「覚悟」という言葉を聞いて、私はぎょっとした。
自分にそんな覚悟はあるのだろうか?
いや、絶対に嫌だ。
常に衛生管理を厳重にしなければならない爆弾のようなものを抱えて、残りの人生を謳歌することなどできようか。
妻とはもっといろんなところに自由気ままに旅行にも行きたい。
それは私が障がいとなって以降、妻には常に下の世話などたいへんな部分の介護をしてもらっていたことに対するせめてもの思いだった。
しかし、そんな状態では旅行どころか、今以上に妻の負担を増やすことになりかねない。
私の人生というよりも、妻の残りの人生に影響を及ぼす問題だった。
それを考えると自分が情けなくなった。
すっかり気心の知れた病棟の看護師さんたちとは、毎日他愛のない楽しい会話をしていたものの、21時の消灯時間以降は急に先の将来のことが頭をもたげてきて、一向に寝むれない日が続いた。
あってはならない状態を想像すると、勝手に心臓がバクバクし出した。
もうサスケ工房も辞めてしまって、障害年金だけで大人しく細々と過ごすことまでが頭をかすめた。
人生において何が大切なのか。
急に働くということは絶対ではないと思い始めた。
家族と老後まで楽しく暮らすことを優先したい。
人間の尊厳や自己実現など二の次だ。
せっかくサスケ工房という最高の働き場所を見つけ、かつての高い勤労意欲を取り戻しつつあったのに、また逆戻りしようとしていた。
毎日がしんどかった。
おそらく過去の入院、あるいはその後の入院含めて、一番しんどい時期だった。
入院中の野球応援
入院してから1か月が経ち、いよいよ高校野球の愛媛県大会が始まった。
息子の高校はなんと開会式直後の第1試合を引き当てていて、しかも対戦校が過去に全国制覇の実績がある強豪校だったのだ。
対戦相手としてはやや不運だったが、開幕試合は必ずテレビ中継されるので、入院中の私にとっては嬉しい面もあった。
ただ、息子が試合に出場できるかどうかはわからなかった。
相手が強豪ということもあり、当然ながらエースの先輩が先発することは決まっていた。
以前なら、二番手投手としての可能性があったのだが、後輩の1年生のなかにも有望な選手がたくさんいるので蓋を開けてみないとわからないというのが正直なところだった。
開会式が終わり、いよいよその試合が始まろうとしていた。
その矢先に看護師が検温にきて、私の血圧を測ったのだが、いつもより血圧が高くなっているとのことだった。
さすがに胸の高鳴りを抑えることができていなかったようで、その看護師には笑われた。
本来なら他の父兄とともに球場で応援していたはずだった。
しかしベッドの上であっても、応援する気持ちだけは負けていなかった。
試合が始まると、選手たちの一挙手一投足を見守り続けた。
そして試合は思いのほか善戦し、6回が終わった時点ではなんと3対2でリードしていた。
そのままエースの先輩は7回のマウンドにも上がり、試合展開によっては完投もあり得ると思われた。
しかし、ここから強豪校が地力を見せ始める。
一気に4点を取られ、あっという間に逆転されたのだ。
そして、ここでついにピッチャーの交代が告げられた。
この瞬間、私の胸の高鳴りがピークに達した。
息子の名前がアナウンスされるのをひそかに期待していたのだが、チームで唯一の左投げの一年生の名前が呼ばれた。
アナウンサーからも「なんとまだ1年生ですよ」という感嘆の声が出た。
結局その回はもう1点を取られたものの、監督の意図通りの役目は果たした印象だった。
そして、9回までその一年生が投げ抜き、試合もそのスコアのままで、試合は終了した。
先輩の三年生にとってはあまりにも早すぎる最後の夏の大会だった。
選手も父兄も泣いている姿が、テレビ画面越しに映し出された。
私もその様子に思わずこみ上げてくるものがあった。
中継の最後のほうでベンチの様子が映り、一瞬だが息子の姿を目にした。
息子が試合に出られなかったことについては確かに残念ではあった。
でもまだ二年生なのでもう一年ある。
息子にはあと一年悔いのないように頑張ってもらいたい。
父親としてそう言いたかった。
そのためには自分も頑張らないといけない。
しかしそう思えば思うほど、どう頑張っていいのかがわからなくなっていた。
追い越された親と子
サスケ工房に入ってから3度目の入院は結局のところ約2か月半かかった。
ちょうどお盆休みに差し掛かるころに退院し、無事に自宅に戻ることが出来た。
いつもならお盆は隣の実家に親戚で集まるのだが、私はあまり長時間座らないほうがいいということで、少しだけ顔を出しすぐに自宅に戻った。
サスケ工房への復帰時期についてもかなり悩んだ。
9月から復帰もできそうではあったが、ややトラウマに近いものもあり、いつも以上に慎重になっていた。
施設長のHさんに連絡して話し合った結果、9月一杯までは自宅療養で様子を見させてもらい、10月頭から復帰することになった。
入院中に気持ちが萎え、働くことにも懐疑的になってしまっていたころから比べると、少しは前向きにはなっていたものの、どちらかというと虚無に近い心境だった。
何か先の目標を立てるような気持ちにもならず、ただ何事もない日常を過ごせれば、それが一番幸せなことだということをあらためて感じていた。
私のことよりもむしろ、向こう1年間の息子のことのほうが気になるところだった。
息子は最上級生となっての新チームにおいて、残念ながらエースナンバーをもらえることはなかった。
エースに選ばれたのは、リハビリでお世話になったS先生の息子さんだった。
新チーム結成後の新人戦や9月の秋の地区予選はいずれも応援に駆け付けることもできなかったのだが、息子は代打での出場こそあったものの、ピッチャーとして登板することはなかった。
後輩に抜かれたことは本当に悔しかったに違いない。
しかしその悔しい気持ちは決して親には見せなかった。
やがて10月になり、いよいよサスケ工房への三度目の復帰を果たした。
約4か月ぶりの復帰だったのだが、最初の通所時に少し驚くことがあった。
まだ利用者としては半年ほどだったFさんが、練習中の利用者を集めて定期的な勉強会を実施していたのだ。
Fさんがレベルの高い利用者であることはわかっていたのだが、それにしてもこの入院中の進展の早さに本当に驚かされたものだった。
事業所の人数も増えてきたことから、さすがに職員のTさんやONさんも実務中心で手一杯になってしまったため、練習についての指導は優秀だったFさんが任されたのだった。
そのことについては納得だったが、ほんとうはそのポジションは自分がやるべきところだったはずなのにという気持ちがあったのも事実である。
何度も同じことを繰り返している間に、会社も世の中もどんどん進んでいるのだということを痛感した。
そして、この何とも言えない気持ちはつい最近感じたばかりだったことにも気づいた。
そうだ。
息子も私も、追い越された立場という意味では全く同じだったのだ。

36歳の冬、先天性の脊髄動静脈奇形を発症。 リスクの高い手術に挑むが最終的に完全な 歩行困難となり、障がい者手帳2級を取得。当時関東に赴任していた会社を辞め、地元の愛媛新居浜に戻り、自暴自棄の日々を過ごす。
41歳の冬、奇跡的にサスケ工房設立を知り福祉サービス利用者として8年半、鉄骨図面チェックの仕事に従事する。 50歳で一念発起しサスケグループ社員となる。
これからの目標・夢
障がいで困っている人の就職のお役に立ち、一人でも多くの仲間を増やすこと。