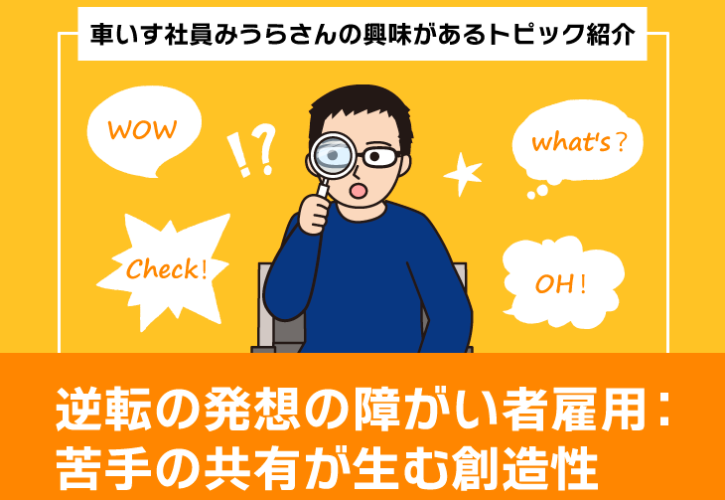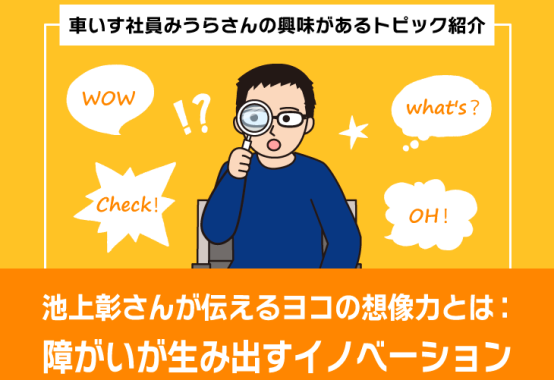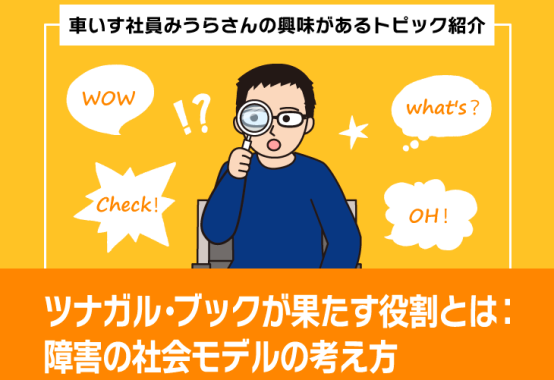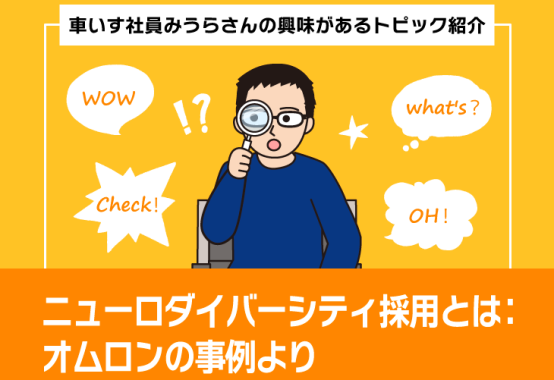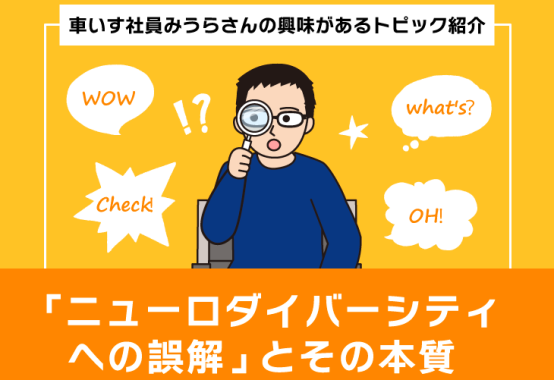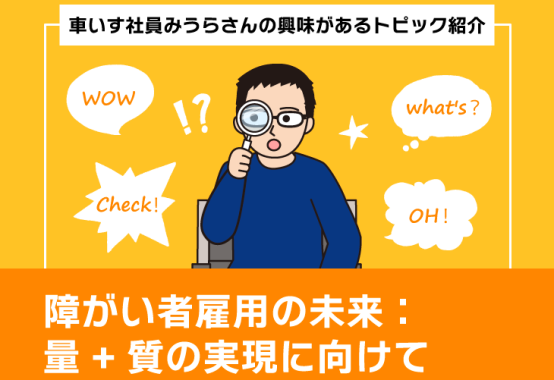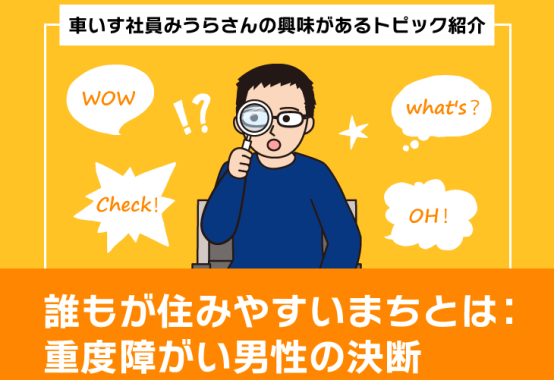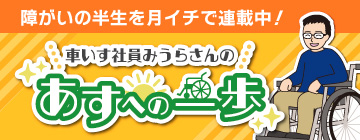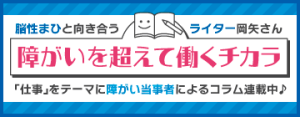「障がい者雇用」と聞くと、多くの人がまず思い浮かべるのは、「配慮が必要な人に、できる範囲で仕事を与える」といった保守的な発想ではないでしょうか。
しかし、以下に取り上げた記事では、そうした従来の見方を根底から覆す、“攻め”の発想で障がい者雇用に取り組んでいる事例として紹介されていたのです。
「強みを活かす」よりも前に、必要なこと(日経BP_2025.04.10)
その核心にあるのは、「強みを活かす」ことよりも先に、「苦手を共有する」ことの重要性を認めるという、まさに逆転の発想です。
そこで、今回の記事の中で特に印象に残った個所を引用しつつ、私なりの感想をまとめてみました。
“「苦手を共有するのが、力を発揮する上でまず大事だと思います」”
この記事の中で最も衝撃を受けたのがこの一言です。私たちはこれまで、「苦手を克服する」「できないことを減らす」ことが、成長や活躍への道だと教えられてきました。
とりわけ障がい者雇用の現場では、本人の“できること”に合わせて仕事を割り振るのが一般的なアプローチです。
しかし、この記事で紹介されたチームはまったく逆の道を選んでいます。
「苦手を共有すること」こそが、その人の力を最大限に発揮するための第一歩だというのです。
この発想の転換は、障がい者雇用のあり方としては斬新でした。
“「チームで互いに苦手を共有していると、自分の力を存分に発揮できる感じがします」”
この言葉は、心理的安全性の重要性を如実に表しています。
苦手や弱みをオープンにできるということは、組織内で信頼が築かれている証であり、そうした土壌の中でこそ、本当の意味で「全人的に」仕事に没頭できるのだと感じました。
人は誰しも、得意不得意の凸凹があります。それを無理に均そうとするのではなく、あえて「凸凹のまま」を活かすことで、互いの補完関係が生まれ、チームとしての創造力が引き出されているのです。
“ADHDのAさんは、当初基本的なPC操作もおぼつかない状態でした。しかし、「パソコンと向き合っている時に彼はどうも楽しそうだ」と気付いたスタッフが初歩的なDX研修の受講を勧めると、高い集中力を発揮してすぐにスキルを習得。研修の難易度を徐々に上げ、ついには東大メタバース工学部のカリキュラムを修了する程に高いスキルを身に着けました。”
このエピソードもまさに「逆転の発想」を象徴しています。
最初は「この方に事務作業は難しい」と評価されていたAさんが、やがてチームの中核となり、組織にDXをもたらす存在になる。
この変化は、本人の努力だけでなく、「彼が楽しそうにパソコンに向き合っている」というスタッフの観察と、そこから始まる丁寧な伴走があってこそ実現しました。
本人すら気づいていなかった「強みの芽」を見逃さず、信じて育てる。このようなアプローチこそ、障がい者雇用の現場にもっと広がってほしいものだと感じます。
“「成長意欲・ポテンシャルの高い人材」という判断軸を持っており、時には数年かけて見きわめた上で採用しています”
この姿勢は、即戦力を求める一般的な採用とは大きく異なります。
特に障がい者雇用では、「今この業務ができるかどうか」が重視されがちですが、ここでは「将来的にどんな可能性を持っているか」が評価されている。
しかも、成長を急かすのではなく、数年単位で丁寧に関わりながら、その人の中にある種をじっくり育てていく。
この“育成”の視点が、真に人を活かす組織づくりの鍵だと思います。
“「自分の持ち味がわかると仕事がしやすくなりますよ。一緒に進んでいきましょう」”
この言葉は、伴走者としての支援者のあり方を象徴しています。
支援とは、指導や矯正ではなく、その人の過去や特性、価値観に深く寄り添いながら、一緒に歩んでいくプロセスなのだと改めて実感しました。
支援者が持ち味を引き出すためには、まず「苦手」に目を向け、受け止めることが欠かせません。
人は、自分の弱さを肯定してくれる存在と出会った時、本当の意味で安心し、自分の可能性に挑戦できるようになるのだと思います。
“自己防衛をできる限り減らして、全人的に仕事に打ちこめるよう注力している”
つまり、「創造性を発揮するためには、自己防衛の壁を取り払うことが必要だ」ということです。
評価を気にして弱みを隠し、無理に“平均的な人材”を演じることで、本来持っている創造力や意欲が押し込められてしまう。
この問題は、障がいの有無にかかわらず、多くの職場に共通する課題です。
むしろ、障がい者雇用の現場からこそ、「苦手を受け入れ合う文化」の価値が広まり、日本社会全体の働き方に変革をもたらす可能性をも秘めているのではと感じました。
“強み、強みとよく言うが、強みを発揮するには、苦手や弱みを隠すのにエネルギーを浪費しない環境が必要”
この言葉は、まさに本記事の核心を突いています。
「強みを活かす」という言葉は美しく聞こえますが、実際には“強みを出せる環境”が整っていなければ意味がありません。
安心して弱みをさらけ出せる関係性と、補い合うチーム文化があって初めて、人は自分の持ち味を活かせるのです。
つまり、強みを活かす前にまず必要なのは、“弱みを受け止める器のある職場”をつくること。
その逆転の発想が、ここに描かれたチームの力の源泉だと感じました。
まとめ
障がい者雇用をめぐる議論は、これまで「できる仕事を探す」「特性に合わせて業務を調整する」といった視点が中心でした。
しかしこの記事が示すように、「苦手の共有」や「ポテンシャルのインキュベート」といったアプローチは、その枠を超えて、すべての働く人にとって意味のある知見を提供しています。
逆転の発想とは、単なるアイデアの転換ではなく、相手の可能性を信じること。
そして、弱さをさらけ出す勇気と、それを受け入れる文化を育むこと。
障がい者雇用の現場から生まれたこの実践が、未来の組織のあり方を示していると感じずにはいられませんでした。

サスケ業務推進事業部
36歳の冬、先天性の脊髄動静脈奇形を発症。 リスクの高い手術に挑むが最終的に完全な 歩行困難となり、障がい者手帳2級を取得。当時関東に赴任していた会社を辞め、地元の愛媛新居浜に戻り、自暴自棄の日々を過ごす。
41歳の冬、奇跡的にサスケ工房設立を知り福祉サービス利用者として8年半、鉄骨図面チェックの仕事に従事する。 50歳で一念発起しサスケグループ社員となる。
これからの目標・夢
障がいで困っている人の就職のお役に立ち、一人でも多くの仲間を増やすこと。