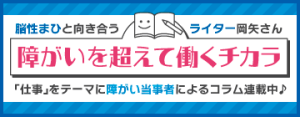最後の打席
「まだ小さいし、大したことないだろう」
妻にスマホで撮ってもらった左側座骨部の褥瘡をみて、私はすぐにそう返した。
内心では「しまった」と思っていたはずだが、そのときは息子の最後の勇姿を見届けたいという気持ちが高ぶっていて、その後から気をつければいいという短絡的な考えでいた。
妻はそれでもしばらく反対していたが、最終的には私が怒り出したのでしぶしぶ受け入れるような形になってしまった。
そして、大会当日を迎えた。
地元の市営球場に駆け付けると、いきなりの関門が待ち構えていた。
1塁側の応援スタンドに行くためには、まずかなりの段数がある階段を上らなければならなかったのだ。
昔からの球場ということもあり、当然ながらエレベーターなどの設備はなかった。
私と妻が呆然と立ち尽くしていると、久しぶりに会う父兄の一人が気づいてくれた。
「これは車いすだときついね。ちょっと、他の人に声をかけよわい」
その人は、実は息子に喧嘩を仕掛けた子のお父さんだった。
自身も高校まで野球をしており、もう一人の長男を含めての典型的な野球一家であり、当然ながら父兄の中でもリーダー的な存在だった。
非常に熱い人で息子同士の喧嘩のときは、目に涙を浮かべて私に土下座をしてくれた。
そのお父さんのおかげで、瞬く間に3人の男の方が加わり、車いすを四方で取り囲む形でスタンドのところまで引き上げてくれたのだ。
申し訳ないという気持ちとありがたいという気持ちが交錯しながら、一人一人にお礼をした。
「いやいや、降りるときもまた言ってよ。それより今日は勝たないかんね」
お父さんはそう言って笑顔を見せた。
かつてはお互いの息子のことでギクシャクもしたが、今は親子共々気持ちはひとつになっていた。
そして、ついに試合が始まった。
練習試合では勝ったことのない相手だったが、思いのほか善戦し1対1のまま最終回にまでもつれこんだ。
息子はそれまでノーヒットだったが、7回表の先頭バッターとして中学最後の打席となる場面を迎えた。
祈るような気持ちで、左打席に立った息子の背中を凝視した。
そしてその初球、相手のストレートのボールを積極的に振った。
打球はセンター前に転がった。
一塁ベース上に立った息子は、スタンドからの大きな声援にはにかんだ。
息子のヒットを間近で見たのはこの時が初めてだった。
思わず涙が出た。
試合は結局その回に点を取れず、最後は満塁での押し出しサヨナラ負けとなった。
チームメイト、そしてスタンドにいた父兄のほとんどが泣いていた。
私も泣いたが、おそらく他の父兄とはまた違った意味合いが強かったかもしれない。
入院以降、親としてろくに応援もしてやれなかった私にとって、その日は特別なものになった。
突然の異変
息子の総体も終わり、高揚感に包まれたなか妻とともに帰宅した。
「座り過ぎとるけん、お尻を確認しよ」
妻からそう言われ、ハッと我に返った。
褥瘡が出来ていたことなど、すっかり頭から消えていたのだ。
試合後も父兄や顧問の先生とずっと話し合ったりして、かなりの長時間座り続けていた。
すぐに妻に見てもらうと、やはり褥瘡の赤みが増し、滲出液も少し出始めていた。
「ちょっと昨日よりも褥瘡が深くなったような気がする。月曜に病院行こや」
妻からそう促されたが、月曜に病院に行くということは、つまり仕事を休みにしないといけないということだ。
本来なら自分の体を最優先に考えるべきなのに、なぜかそのときは休みまで取って行くということについて抵抗感があった。
「いやいや、来週もやらんといかんことも結構あるし、午後の在宅作業で合間に横になったりするから大丈夫、大丈夫」
今考えれば、なぜそのような判断をしてしまったのか自分でも理解ができない。
結局、妻の言う通りにせず、家にまだ残っていたゲンタシンを褥瘡部に塗ってもらい、私は翌週もそのまま午前通所、午後在宅での作業を毎日繰り返してしまった。
念のため作業が終わると必ず妻に褥瘡を確認してもらっていたが、妻が言うには表面積こそ変化はないものの、徐々に色目と深さが変わってきているということだった。
その間も妻から病院に行くことをしつこく促されたが、特に熱が出るというような反応がないことをいいことに全く応じようとしなかった。
そして、ついに異変が起きる。
総体の日から11日目の月末付近の水曜日のことだった。
その日の朝、起きるといつもと違って微かに気だるさを感じたのだ。
最初は気のせいくらいにしか受け止めていなかったのだが、朝食を取ったあとこれから通所の支度をしようというタイミングで、その気だるさがひどくなってきた。
もしやと思って、すぐに体温計で熱を測った。
体温計が鳴り、すぐ取り出した。
37.9度と表示されていた。
時間にしてどのくらいだろうか。
自分の体感としては一分間くらい、その表示を見つめ続けていたかもしれない。
「やってしまった」
心の中でそう呟いた。
大きな代償
すぐに会社に電話し、Hさんに症状を説明し病院に行くため急遽休むことを伝えた。
病院に行く車中、妻に「あれだけ注意したのに」とずっと怒られっぱなしだった。
それに対しては何の反論もできず、私はただひたすら黙っていた。
病院に着くと、朝のため多くの外来患者がいたが、運よく形成外科は空いていてすぐに先生に診てもらえることになった。
先生は私の左側座骨部を見るや否や、「ああ」という声を漏らした。
その後、しばらく黙ったまま処置をしていたが、時間にして5分もなかったと思うがその時間がかなり長いものに感じられた。
「うーん、中を少し削って確認したんですけど、思ったより深いですね」
先生が重い口調で私にそう言った。
「前回の右側くらいの状況でしょうか?」
「そこまでではないですけど、このままだともっと悪化していく可能性がありますね」
私の問いに対する先生からのその言葉で、胸の高鳴りを感じた。
「こんな状況になる前に来てもらえればよかったんですけど、さすがに今回も手術が必要になると思います」
病院に向かう車中である程度覚悟を決めていたとはいえ、先生からそう告げらると具体的に入院の二文字が浮かんできて、前回のことを思い出した。
つまり2年前に半年間にも及ぶ入院をし、結局手に入れていた仕事を自らの事情で手放すことになってしまったことだ。
今回も同じことになってしまうのか。
そう思うだけで、私の胸の高鳴りはさらに音を立てるかのように増していた。
サスケ工房の人たちの顔が目に浮かんだ。
「今頃、いつものようにみんなで侃侃諤諤と楽しくやっているんだろうなあ」
そう想像するだけでなにか切ない気持ちになってきた。
たった2年前に起きた事実によって、私は一種のトラウマを感じ始めていた。
サスケ工房も辞めなければならないのか。
どうして、同じことを繰り返してしまうのか。
気だるさも相まって、私は自分自身の不甲斐なさにいら立ちを覚えた。
「とりあえず、すぐに入院の手続きをしてください」
先生からそう言われると、私は恐る恐る聞き返した。
「今回の入院もだいぶ長くなるのでしょうか」
先生は少し困ったような表情になり、しばし沈黙をした後に口を開いた。
「うまく行けば前回よりは速く退院できると思います。それでも2か月くらいは見ておいてください」
その言葉で若干だが私の心は落ち着きを取り戻した。
その後、速やかに入院手続きに入り、前回とは違う3階の病棟への入院が決まった。
もはや自分の取った行動の何が正しいのか正しくないのかはわからなかった。
しかし、大きな代償となったことだけは確かだった。

36歳の冬、先天性の脊髄動静脈奇形を発症。 リスクの高い手術に挑むが最終的に完全な 歩行困難となり、障がい者手帳2級を取得。当時関東に赴任していた会社を辞め、地元の愛媛新居浜に戻り、自暴自棄の日々を過ごす。
41歳の冬、奇跡的にサスケ工房設立を知り福祉サービス利用者として8年半、鉄骨図面チェックの仕事に従事する。 50歳で一念発起しサスケグループ社員となる。
これからの目標・夢
障がいで困っている人の就職のお役に立ち、一人でも多くの仲間を増やすこと。