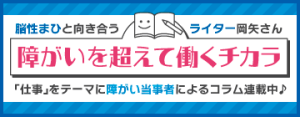初めての入院生活
手術を終えてから、私にとって初めての長い入院生活が始まった。
急性期病棟の個室でトイレもあったが、もちろん自分の足で移動することはできない。
看護師の介助を受けながら車いすでトイレへ行くことになるのだが、ここで予想外の事実を知る。
自力で尿を出すことができないのだ。
とりあえずは、尿道に管を入れてウローパック(蓄尿袋)で対応することになった。
排便に関しては、なんとか自力で出すことができたが、以前に比べるとだいぶ時間がかかる。
またお風呂代わりとなるシャワーに関しては当面は週1回で、毎日看護師に清拭をしてもらうことになるのだが、さすがに下半身を拭いてもらうことにも抵抗があった。
そんなこともあり、最初のころは何かにつけてイライラしていたように思う。
何かの手違いで予定の入浴時間に看護師が迎えに来ないときは、何度も呼び出しボタンを押し、怒鳴ったりしている自分がいた。
消灯は21時で、それまで午前様だった自分にとってはあまりにも早い就寝だった。
日によってはこの先どうなるのだろうと不安で眠れなくなったりしていた。
気分転換で外に出たくても、自分で勝手に動くこともできない。
まさに牢屋に閉じ込められている感覚に等しかった。
当時は今のようにスマホもまだ所有していない頃だったので、テレビが唯一の気晴らしだった。
何もかもが戸惑う毎日で、それまで当たり前に思っていた日常がどれだけ幸せなことだったのかを気づかされた。
そんな日々を過ごすなか、女性の作業療法士と男性の理学療法士が部屋を訪ねてきて、リハビリを開始することの説明を受けた。
先生からは、手術自体は理論上は失敗ではないので、術後のリハビリによる回復の可能性があることを聴かされていた。
半信半疑のなか、翌日から午前に20分間、午後に20分間のリハビリをすることになった。
数々の励ましと回復の兆し
入院してから1か月くらい経った頃、当時勤めていた会社の全社員から、寄せ書きや手紙、そして各部署・拠点ごとに束ねられた千羽鶴が届いた。
以前の部署でお世話になった上司や部下からのメッセージには思わず目頭が熱くなってしまった。
職場の所長や部下、事務員さんからは、入れ替わり立ち替わり何度もお見舞いを受け、職場でのエピソードなどを交えながら、落ちこんでいる私を笑わせてくれた。
そして一番驚いたのが、愛媛本社にいる常務が多忙のなか群馬までお見舞いに訪れたことだった。
所長から、社員全員のメッセージを提案したのが常務だと聞いていたので、その感謝を伝えた。
普段は厳格なイメージの常務が、全く違う柔和な笑顔だったことが今でも印象に残っている。
数々の励ましが力となったのか、全く動かなかった右の足首が少し動くようになり、2か月経った時点で多少地面に対して踏ん張る感覚が得られた。
懸案だった排尿に関しても、専用キットによる自己導尿のやり方を会得し、ウローパックをつけずに過ごせるようになった。
3か月目には急性期病棟から一般病棟に移り、4人部屋で過ごすことになった。
脳梗塞などそれぞれ事情を抱えた人たちと和気あいあいと話し、ときには励ましあいながら日々リハビリに励んだ。
その甲斐もあってか、元々問題のなかった右足のほうの膝が少しずつ動くようになった。
そして4か月目にはリハビリ時間をそれまでの倍に増やし、なんと歩行器による歩行練習ができるまでになったのである。
リハビリの限界
「もしかしたら、自力で歩けるようになるかも」
ふとしたときに、このことが頭をよぎるようになる。
左足は相変わらず微動だにしなかったが、右足の回復により歩行器での練習からいよいよ二本杖による歩行練習まで到達したのだ。
ちょうどそのころに入院してから半年を迎えることになり、医療保険の関係でリハビリ通院に切り替えることになった。
エレベータのない3階建てアパートの3階に住んでいたため、今思えばかなり危険なことだったと思うのだが、これもリハビリと自分に言い聞かせながら、二本杖で一段一段ゆっくり時間をかけて階段を上がっていった。
調子の悪いときは、階段で何度も転びかけたが、妻や息子が必ず支えてくれた。
夏場だったので、上がり切ったときは汗がだくだくで、体力を相当消耗していた。
だがそれよりも住み慣れた家で家族と一緒に生活できることが何より嬉しかった。
息子から、私の入院中に始めた野球のことや他愛のない学校の話を聴いたり、妻の料理を毎日食べられるだけで幸せだった。
ただ一方で、一抹の不安も感じていた。
それは、退院前あたりから回復の伸びが急に感じられなくなっていたことだった。
先生からは急性期から半年間でどこまで回復するかと言われていたが、まさにその時期を境に、伸びを感じるどころかむしろ右足の動きの後退をかすかに感じ取っていたのだ。
当初はそのことを自分のなかで気づかないふりをしていた。
しかし通院に切り替えてから1か月経った頃には、階段で上がることはもはや厳しくなっていた。
さすがにその現実を受け止めざるを得ず、たまたま1階の部屋が空いていたのですぐに引っ越しをした。
同時に病院からも、車いすの購入と障がい者手帳の申請をすすめられた。
先生からは再手術をしないと、このままでは厳しいかもしれないという診断がくだった。
もはやリハビリには限界があることを認めざるを得なくなった。
ここから再び、不安と葛藤で眠れない日が続くことになる。

41歳の冬、奇跡的にサスケ工房設立を知り福祉サービス利用者として8年半、鉄骨図面チェックの仕事に従事する。 50歳で一念発起しサスケグループ社員となる。
障がいで困っている人の就職のお役に立ち、一人でも多くの仲間を増やすこと