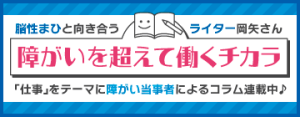褥瘡悪化による入院
先生の「即入院」という言葉で全てを察した。
やはりというべきか、褥瘡が悪化し感染を起こしていたのだった。
先生はその場ですぐに褥瘡の箇所を切開し、壊死した組織を焼いて取り除く応急処置をした。
信じられないことに、膿の蓄積によりゴルフボール分の空洞ができてしまっていて、ほぼ骨が見える範囲まで壊死が広がっていた。
「ここまでくると、他の皮膚からの移植手術をするしか治す手立てはありません。ただそのためには壊死部分を完全に取り除くための除去手術を先にする必要があります」
高熱で朦朧とする意識のなか、先生のその言葉を聞き、今更ながらに後悔した。
なぜもっと気をつけなかったのか、この後薬局での仕事はどうなってしまうのか、熱はどこまで上がってしまうのだろうか、などの感情が頭の中を駆け巡った。
「いずれにしても、まずは抗生剤の点滴で感染による炎症を抑えなければいけません。すぐ入院してください」
先生からそう告げられ、そのあとすぐに急性期病棟に入院することになった。
病室のベッドで、再度体温を測るとほぼ40度近くまで達していた。
体が燃えるような熱さを感じ、看護師の入院案内の説明や聞き取りにも受け応え兼ねていた。
血液検査による炎症反応や白血球の数値も目を疑うレベルの異常値を示していて、直ちに抗生剤の点滴を開始したものの、熱はいっこうに下がらない。
あまりのしんどさに、このまま死んでしまうのではないかと思うくらいネガティブな気持ちに追い込まれてしまっていた。
そのような状況のため、会社への連絡は妻にお願いし、しばらく休職する旨を伝えてもらった。
つまり、仕事を始めてからわずか1週間も経たないうちにリタイアすることになったのである。
前の日まで意気揚々と新居浜駅に向かって通勤していた姿がまるで嘘のようだった。
3年前に脊髄動静脈奇形で入院した時に、さんざん妻や息子そして両親に心配をかけ、もう二度と家族に辛い思いをさせないようにと思っていたのに、またこんなことになるなんて。
自分が本当に情けなかった。
そしてその日からしばらく、後悔と熱にうなされる日々が続くのだった。
苦難と葛藤の日々
褥瘡による感染は想像以上に深刻なものとなり、入院から1ヶ月経っても熱は38度を切ることはなかった。
しんどくてたまらないときは、解熱剤で一時的に熱を下げたりもしたが、その間に大量の汗が出るのが苦痛でたまらなかった。
汗が引くとともに熱は37度台半ばまでは下がり、一時的に楽にはなるのだが、半日もするとまた熱は上がるという状況を繰り返した。
抗生剤の種類も色々変えてはみたのだが、どれも効き目が今一つで、先生も首を傾げるほどだった。
そんななかある日、社長のMさんからメールでの連絡があった。
とりあえず私が抜けた穴は、午前中だけパートを雇い、午後はMさん自ら応援に入るなどして対処しているから大丈夫とのことだった。
熱が落ち着く頃に一度お見舞いに行きたいとのことだったが、いつ熱が下がるとも言えない状況のため、その気遣いが逆に心苦しかった。
このままだと壊死組織の除去手術すらいつになるのか分からず、先が見えないなか当分の間、会社に余計な負担をかけ続けてしまうのだ。
また仮に復帰できたとしても、その後体調を安定させて働くことはできるのかどうかもわからなかった。
一度移植手術で治した褥瘡はよほど気をつけないと再発しやすいと言われていたからだ。
妻や両親も、復帰することに対してやや懐疑的だった。
結局、メールの返信ではその胸の内を伝えることはできず、お礼とお詫びをするのが精一杯だった。
それ以降、毎晩のように復帰すべきかどうかの葛藤の日々が続いた。
熱が38度を切り始めたのは、入院してから2ヶ月が経った頃だった。
不思議なもので、37度台まで下がると体感的にはまるで平熱なのではないかと錯覚するくらいの感覚になっていた。
解熱剤を使うこともなくなり、9月に入ってやっと、壊死組織を完全に除去するデブリードマンと言われる手術に踏み切ることができたのだ。
手術は、局所麻酔で約1時間半程で無事完了した。
術後にその箇所を写真画像で見せられたが、坐骨の一部がはっきり見えるくらい、肉がぽっかりと大きくえぐりとられていた。
痛々しいその穴が、自分の身体の一部分だとは信じたくなかった。
先生から、次の移植手術に向けてここから約1ヶ月は毎日滲出液の洗浄をしながら、新たな肉芽が再生される最適な状態を待たなければならないという説明があった。
移植後も1ヶ月間は座位禁止で完全寝たきりになると言われていたため、その後のリハビリ期間などのことまで考えると、退院時期はどう見積もっても年内一杯かかる計算だった。
入社して早々に半年も休職してしまう話などまず聞いたことがない。
想像もしていなかった厳しい日数を突きつけられて、葛藤していた私の気持ちはある方向に固まりつつあった。
入院中の退職
Mさんがお見舞いに来てくれたのはそれから1週間が経った頃だった。
「今回はこんなことになってしまい、本当に申し訳ありません」
私がそう言うと、Mさんは柔和な笑みを浮かべながら、首を横に振った。
「だいぶ無理をさせてしまったようで、こちらこそ申し訳なかったね」
そう言われて逆に謝られてしまい、ただただ恐縮するしかなかった。
それから私の病状のことや薬局の様子のことをしばらく話し合った。
私がいきなり抜けたことはかなりの誤算だったと思われるが、Mさんはそのような感情をおくびにも出さなかった。
むしろ、私の気落ちしている様子を察してか冗談を交えながら、何の問題もないからと念押しするように言ってくれた。
ひとしきり話を終えると、Mさんは話題を少し変えて、仕事の合間を縫って趣味で執筆している小説のことに触れた。
そして、長い入院での退屈しのぎにでもなればと、Mさんが参加している文芸の同人誌を一冊渡してくれた。
Mさんは多趣味で、薬局経営の傍らで小説を書いたり油絵を描いたりしていた。
いずれもかなり本格的なもので、時間をかけたものだったが、ただでさえ多忙のなかどこからそんなバイタリティが湧き出るのだろうと思う程だった。
そんな小説の話を聞いているうちに、気がつくとMさんが来てからすでに1時間も経っていた。
「長くなってしまったのでこの辺でそろそろ。まあ、焦らず気長に療養してください。みんな元気になって復帰されるのを待っていますから」
Mさんはそう言って帰り支度を始めた。
「あ、ちょっと待ってください」
自分でも驚くタイミングで思わずMさんを呼び止めた。
もうこのタイミングで伝えるしかない、と思ったのだ。
「入院してからずっと仕事の復帰のことについて悩み続けていたんですが、再発のリスクのことを考えると、やはり薬局での仕事は難しいという結論に至りました。出来ればこの時点で辞めさせてもらえないでしょうか」
そう言うのが精一杯だった。
それが恩を仇で返す言葉であることはわかっていたが、毎晩葛藤したうえに出した苦渋の結論だった。
Mさんもさすがに少し驚いていたが、すぐに何かを察したような表情に変わり、やや間があった後、静かにうんうんと頷いた。
「色々悩んだんだろうね。残念ではあるけど、こちらとしても無理は言えないから」
そう言ってMさんは私の願いを優しく受け入れてくれた。
こうして、障がいになってから初めての仕事への挑戦は、入院中に呆気なく自らの意志で終わらせてしまったのだった。
Mさんが病室を出た後、私は何もない真っ白な天井をぼんやり眺めながら、本当にこれでよかったのだろうかと、しばらく自問自答し続けていた。

36歳の冬、先天性の脊髄動静脈奇形を発症。 リスクの高い手術に挑むが最終的に完全な 歩行困難となり、障がい者手帳2級を取得。当時関東に赴任していた会社を辞め、地元の愛媛新居浜に戻り、自暴自棄の日々を過ごす。
41歳の冬、奇跡的にサスケ工房設立を知り福祉サービス利用者として8年半、鉄骨図面チェックの仕事に従事する。 50歳で一念発起しサスケグループ社員となる。
これからの目標・夢
障がいで困っている人の就職のお役に立ち、一人でも多くの仲間を増やすこと。